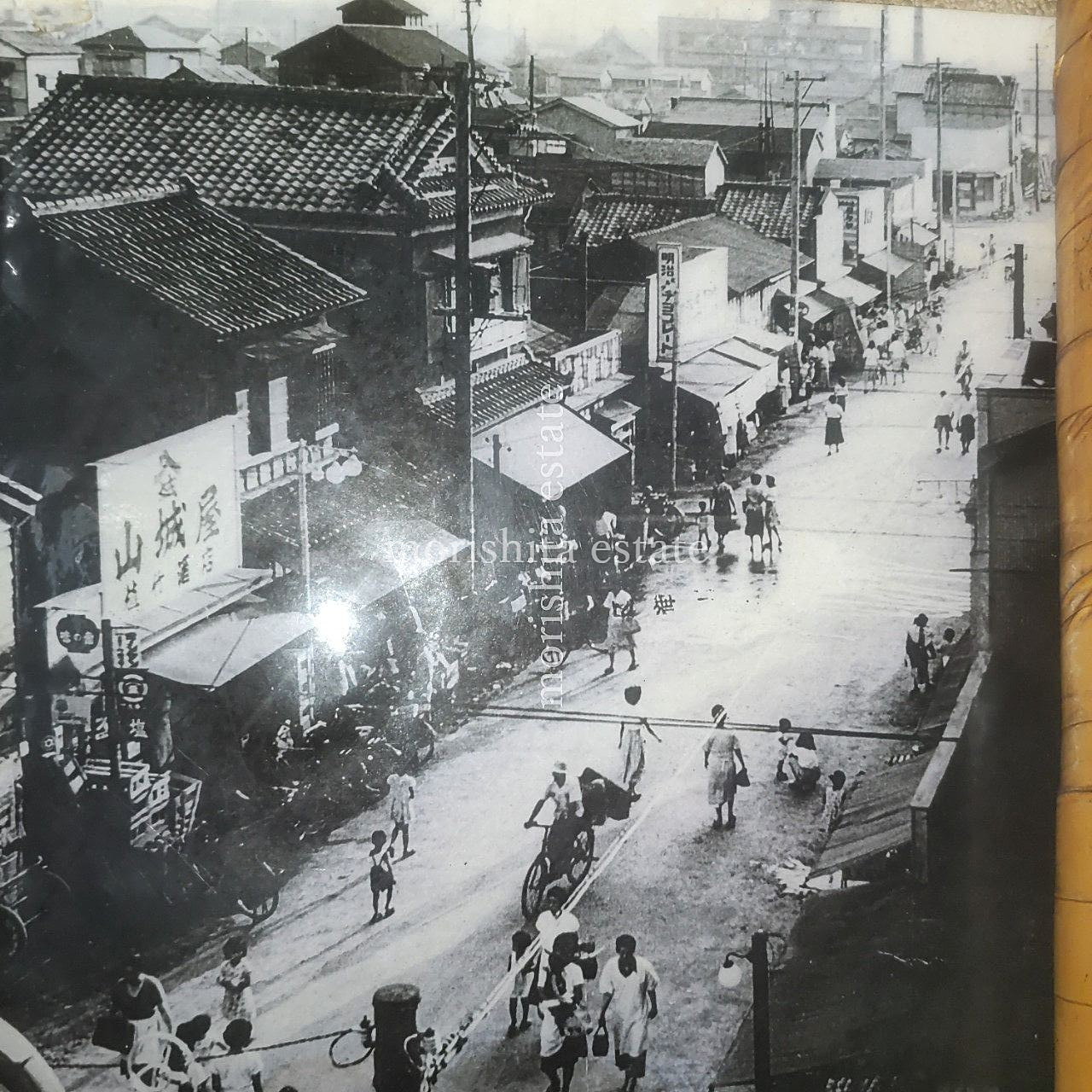『登記簿』記載の専門用語②
家を建てる場合『地目』にご注意下さい。
『地番』は住所(住居表示)と異なる場合が多いです!
3月に入り、厳寒の冬場を乗り越えたような気がします。
とはいえ、3月は『花粉症』の方々には地獄の季節であると言われており、持病をお持ちの方でないと、その辛さが分からず気を使わないと失礼にあたると、よく言われております。
耳鼻科に行くと、かなり待たされる時期でもあり、困惑するものです。
登記用語は、一般の方には難しくて理解できない用語が多くて困るという意見も御座いますので、登記に関する説明を続けてみたいと思います。
1,地番とは⁈
『地番』とは、区分された土地の1筆ごとに定められた番号で、『所在』と共にその土地の位置を示し特定し、『土地の登記簿の表題部』に記載されております。
地番は、法務局が地番区域を定めて、その地番区域ごとに起番して、土地の位置が分かり易い様に整然と、定めなければならないとされています。
現実には、整然としていない区域もあり、特に分筆や合筆が頻繁に行われている区画は、非常に複雑になります。
例えば、分筆前に記載されていた1筆が、3筆に分筆された場合、枝番と呼ばれると土地が新たに付される場合が有ります。
分かり易くご説明すると
1番の土地を、3筆に分筆すると『1番壱』『1番弐』『1番参』と言うように枝番が付されることが有ります。
合筆する場合は、幾つかの土地を纏める行為になります。
例に挙げますと、『1番壱』『1番弐』『1番参』の土地を合筆する際は、『2番』が登記上有る場合、『3番』等に変更される場合が有ります。
尚、『地番』は『住居表示』と異なりますので、郵便等で間違って『地番』にて記載すると、あて先不明にて未到着になる場合もあるので、注意が必要とされます。
都内では、大体『地番』と『住居表示』が異なりますが、地方では『地番』と『住居表示』が同一になることも有りますので、認識されるとよろしいかと思います。
余談ですが、40年近く前の住宅地図に記載されている住所は、当方の知る限り『平成の大合併』にて変更されていることが多いものです。
2,登記の記載の『地目』とは⁈
『地目』とは、土地の利用状況により決められた土地の名称で、土地の登記簿の表題部の記載事項とされています。
地目は、その土地の『主な用途』により、現在23種類に区分して定められています。
『住宅』を建築出来るのは、『宅地・山林・原野・雑種地』の4種類ですが、『地目変更』を行えば建築可能にます。
その他の『地目』で建築できないものは、色々と有ります。
『田・畑・塩田・鉱泉地・池沼・牧場・墓地・境内地・運河用地・用悪水路・ため池・堤・井溝・保安林・公衆道路・公園・学校用地・鉄道用地・水道用地』
上記の『地目』は、読んでみてお分かりと気づく方も多いのですが、それ専用に利用していることが多いものです。
※課税上の土地の評価(国税・地方税)は、地目によって異なりますが、評価上の地目は現況にて評価されます。
ある1筆の土地が、現実にどの地目に該当するのかの具体的認定は、必ずしも容易でななく、一般的な『農地と言われます【田・畑】』を農地以外の『地目変更』するには、『都道府県知事』や『農業委員会』の許可を得ることが条件になります。
ここは面倒な説明になりますが、『テニスコート』や『プール』については、『宅地に接続するものは宅地とし、その他は雑種地とする』等の認定基準もありますので、注意が必要です。
3,家屋番号とは⁈
『家屋番号』とは、建物を特定するために『法務局』が定める番号で有り、建物の名称になります。
家屋番号は、建物登記の表題部の記載事項にされておりますが、原則として地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めています。
例えるならば、『江東区亀戸5番地』の敷地上の建物の家屋番号は、『5番地』となりますが、1筆の土地の上に1つの建物が建築されているとは限りません。
1筆の土地上に幾つかの建物が建築されていると、敷地の地番と同一の番号に『壱』『弐』等の枝番が付けられます。
逆に数筆の敷地の上に1つの建物がまたがり、建築されている場合は原則として『床面積の多い部分の敷地の地番と同一の番号』をもって定められています。
家屋番号が、敷地の番号と同一である建物の敷地上にある他の建物を登記する場合、敷地の地番に『壱』『弐』等の枝番が付けられますが、この場合には、最初に登記された建物の家屋番号は、必ずしも変更する必要はありません。
今回、ご説明する内容は意外と、当方のような不動産業者でも知らないことも多いものです。
お客様から相談された時点で、登記ミスが指摘されることも極たまにありますので、ご注意頂ければと思います。

関連した記事を読む
- 2025/04/01
- 2025/03/30
- 2025/03/28
- 2025/03/25